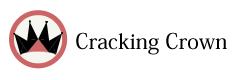はじめに触れたのは、父の書斎でのこと。
小さな書斎の壁は本棚になっていて、まだ私の手には大きすぎる革張りの本が並べられていた。
ずしりと重い本を抜き出し開けば、白と金の光が気泡のように溢れて消えた。
たいそう美しいものであると思った。
けれど、その時の私には、それを伝える言葉が無かった。
父は魔術師に憧れていたのだろう。
少年のような人だったのだ。
そしてその少年のような人は、魔術の代わりに外に目を向けた。
不思議なものを追い求め、外から珍しいものを仕入れては横に流していた。
元は人から頼まれ探すうちに、それが商いの体をなしてきたのだと聞く。
もっとも私にはその成り立ちの詳細などは知らない。
ただ気付けば家には人が溢れ、モノが溢れていた。
私よりも背の高い人々が訪れては、父や姉と何かを話して、そして何かを受け取っていく。
話交わされる言葉はどれも早く、理解をする前に会話は終わっていた。
時折、ただ奥から見ているだけの私に語りかける者も居た。
坊ちゃん
何して遊んでるの?
おいくつなの?
お菓子いかが?
矢継ぎ早に問われる言葉に、返す言葉は出てこなかった。
口からはただ言葉にならない音だけが漏れ、沈黙には遠く誰かの言葉が降り注ぐ。
諦めたような顔をして、皆私の前から通り過ぎる。
妹が生まれたのは、私が十を数えた頃だった。
妹の面倒を見るために母は店に出ることをやめ、代わりに雇人を増やした。
幸いにして家業は順調だった。
忙しなく動きまわる父と姉が食卓に揃うことは無く、
妹と共に休んでいる母が出てくることも無かったが、
それはそれで言葉少ない環境に安心していた部分もあった。
元来機敏な方でも無く、言葉まで遅いとなれば、同年代の友人など出来る訳が無い。
おそらく人間の子とて同じだろう。
声高に笑い、動きまわる子に注目と尊敬は集まるものなのだ。
そして愚鈍な子は、得てして笑われるものなのだ。
しかし、私はからかわれる言葉にすら理解が追いつかなかった。
反応など出来る訳もない。声音を聞くのが精一杯だ。
ほとんど反応を示さない私は、遊ばれる訳でもなく、ただ静かに避けられていた。
さぞ気味が悪かっただろう。私でもそう思う。
あの頃からだろう。
私が獣に傾倒していったのは。
思い出すと苦笑いが浮かぶ。
フロウと名付けた猫が居た。
一般的な愛玩用の猫とは違い、かなり大柄な猫だ。
いつの間にか裏庭に住み着いていたらしいが、
大鼠の類を獲っては誇らしげに掲げ、見事母から庭の番役を任ぜられたそうだ。
白と黄の混じった淡い縞模様に、美しい緑の瞳をした猫だった。
私が寄ると、美しい緑の瞳を細め、喉を鳴らした。
穏やかに横たわる彼女に寄り添って昼寝をするのが、私の日課になった。
喋らない彼女は私の言葉を笑わない。
怒りも泣きもしない私を訝しまない。
途中で止まった言葉を、無理に追うことも無い。
駆けて転んだ私の側で、彼女は寝転ぶ。
私が笑えば目を細めた。
言葉の必要ない交流は、私にとっては何よりも得難い喜びでもあった。
何をしていたか語る必要もない。
何が好きなのかを伝える必要もない。
彼女の隣で本を読み、彼女と共に木に登り(もっともそれは本当にわずかな高さであったけど)
毒虫に触れようとすれば彼女は低く唸り、私はそれを知る。
おやつにと貰った干菓子は半分に分けて食べた。
まるで片割れのように側にあった。
彼女は私の良き理解者であり、そしてまた私も彼女の理解者だった。
ある時までは。
私の方がよほど長い命を持つのだと、知るまでは。
冷えゆく体は次第に水分すら無くし、美しかった緑の目は濁り、小さく息を吸ったきり吐くことはなかった。
それからの数年を、私は殆ど覚えていない。
ただただ目には、父の書斎で見た白と金の光だけが瞬いていた。
目に映る本のすべてを払い落とし、片っ端から読み耽った。
父の収集していた魔法書は私にあらゆる知識を与え、そして私を一層現実から遠ざける。
私が没頭したのは、再生魔法の習得だった。
居るのか、居ないのか。
彼女を戻せるのか?
戻す、それはどこに。
何が足りない。
何もかも足りない。
だって彼女は、私の半身なのに。
うるさく聞こえるのは私の声だけだった。
庭の片隅に、母が小さな墓をこさえてくれていた。
私がその前に立ったのは、彼女の死からすでに数年が過ぎた頃だった。
風もない、穏やかな夜だった。
紙でささくれた指先を振れば、小さな光が生まれる。
目に映る白と金の光が、果たして本当にあったものなのか、今となっては分からない。
これで彼女は戻ると信じていた。信じたかった。
彼女の毛皮には瑞々しい熱が戻り、濁った瞳は再び澄み、そして優しく目を細めるのだと。
馬鹿な子どもの試みは、当然のように成功などしなかった。
そして私はその時はじめて、彼女を無くし、泣いたのだ。
冒険者として家を出る前、小さな墓標の傍らに一本の苗木を植えた。
彼女は木陰で昼寝をするのが好きだったから。
細い苗木はしっかりと根を張り、私が訪れる度に背を伸ばしていた。
豊かな葉が古びた墓標に白と金の木漏れ日を落とす。
花を手向け、私は墓標を後にした。