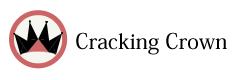所詮、自分たちは手駒の一つでしか無く、血を流すのも、この雪原に足あとを残すのも自分たちで、
そしてあいつらは今頃暖かい暖炉の前で、戦略会議という名の酒盛りを繰り返しているのだろう。
もはや怒りですら、この雪に吸い込まれていくような気がした。いっそ手放してしまえればどれほど楽になれるだろう。白と灰と黒しか映らない視界の端から、極彩色の花が開いていく。いつか故郷で咲いているのを見た事がある。死者への弔い花だ。
開くだけ開いた花はやがて私の視界を覆い尽くし、そしてそこで私の意識は途絶えた。
何かに呼ばれるように意識が戻り、薄い毛布の手触りが夢を見ていたことを私に伝える。夜はまだ明けきらず、窓から差し込むのは月明かりのように見えた。夢というものに、まだ慣れる事が出来ない。黒く塗りつぶされるように意識が吸い込まれる快感こそ知れど、その上で意識を揺さぶられ、眠りながら起こされる感覚が気に入らない。見るものといえば決まってあの日の事となれば、その嫌悪感は募る一方だった。
「……俺も夢に見るよ、たまにな」
隣に座る男が苦々しい顔をして杯を煽った。私は無言で目の前の杯に視線を落とす。
すっかり馴染みになった酒場はまだ人影もまばらで、私と男の他に幾つかささやき交わすような声が聞こえるだけだった。照明が壊れたまま放置されているような酒場ではあるが、安酒を飲みながら気安い話をするには丁度良い位なのだろう。メトセラから訪れる騎士が多いこともあり、冒険者として依頼をこなす傍らに顔を出すことが増えていた。
「はは、もう忘れたとばかり思っていたがな」
「まるで俺が薄情な奴みたいじゃないか」
かつて同僚であった男は、今は団を抜けて小さな雑貨屋を営んでいると言う。団を抜けてと言うよりも、団を抜けざるを得なくなったと言う方が正しい。
「雑貨屋の方は順調なのか」
「ああ、カミさんがよくやってくれてる」
「良い嫁さんを貰ったもんだな」
「来年には子どもも生まれるんだ、驚け」
「ははは、何か祝い品を贈らねばな」
店の扉が鳴り、数人の若者がテーブル席へ腰掛ける。すでに何処かで一杯引っ掛けてきたのだろう。声は大きく、陽気だった。無愛想な店主がどこか鬱陶しそうに眺めるのを横目に、私は茶の入った杯に口をつけた。
「……まだ騎士団に居るのか」
「ああ。しかし、冒険者派遣されている状況を見れば分かるだろう。外されたな、完全に」
「勿体無いな、お前だけじゃなかったのか。五体満足だったのは」
「私ひとり五体揃っていても仕方ないだろう、それなりに痛手も負った」
「そうだな」
男には片足が無い。そして私には、背と手を覆う筈だった鱗が無い。
あの雪の日に、失ったのだ。
あの日、騎士団に舞い込んだのは野盗の討伐依頼だった。自警団で処理すべき問題であるのに、わざわざ騎士団を経由することにそもそも疑問を抱くべきだったのだ。たかが野盗討伐には過ぎる編成が組まれ、そして私はその一員として参加をしていた。男は当時、隊を率いる役を担っていた。
─ 北へ ─
ただそれだけの命令の元、私たちはメトセラを後にしたのだ。
河を越え、ハーケンの脇を抜け、緑深い山々を越え、遠征は長引いた。本隊からの戻れという命令も、野盗らしきものも居なかった。やがて木々が黒く佇み、雪が混じるようになった頃、隊の中で意義を唱える者も増え始めた。本隊から届くのはただただ、北へ向かえ其処に野盗が逃げ込んでいるという情報だけだった。私たちは何処へ向かわされているのか。たかが野盗退治に何故これほどの遠征を続けるのか。野盗など本当は居ないのではないか。まったく目標が見えない遠征は徐々に、隊員の心に疑心暗鬼の影を落とした。
「……結局、何も無かった」
私が呟くと、男は自分の手を見ながら小さく頷いた。
北へ。ただ北へと向かった。足元を覆う雪は柔らかいものから細かい粒子に変わり、吹きすさぶ風には雹が混じる。慣れぬ気候の遠征は、隊員達の心身を確実に削ぎ落としていった。幾人かが脱走をし、今となってはそれは正しい判断であったと思う。彼らは生き延びることが出来たのだろうか。
交替で休息を取る真夜中、隣に居た男がこの腕を切り落としてくれと懇願する。指先が痛くて仕方がないと訴えかける彼の肘から先は、もう既に無い。うわ言のように痛いと繰り返す彼が、翌日立ち上がる事は無かった。雪の中に楽土を認め、走り行く者が居た。呪詛の言葉をまき散らしながら足を止める者も居た。俺たちは捨てられたのだ。この先にも後にも、何があるものか。
一人、また一人と減っていく。雪を踏みしだく音を私はいつでも数えていた。それだけが辛うじて私が私である事を指し示すようで、縋らずには居られなかった。聞こえなくなった足音を振り返る余裕すら無く、ただ歩き続ける私たちは、もはや人でも何でも無い、ただ動き続けるだけの物と成り果てる。
やがて冬の領土と呼ばれる地に差し掛かり、本隊から届いた伝令はただ一言、野盗は駆逐された、それだけだった。
もう考えることすら叶わなかった。戻ろうと振り返る道は雪で覆われ、自分たちの足あとなど見付けられる訳もない。地平線と空に境目は無く、すべてが等しく色を無くしていた。
皮肉にも、戻る私たちを導いてくれたのは弔うことも帰してやることも出来ない隊員達の亡骸だった。いっそ戦で散る方がマシだ。何も分からないまま、草木すら生えない場所に置いていくなどと。
片方の瞼はすでに氷で張り付いていた。目の前を過ぎる吹雪が視界を遮り、すでに感覚を無くして久しい手足はただ重たい。ああ。ああ、私たちは何なのだろう。怒りに任せた叫び声はすぐに、あざ笑うような吹雪の音に飲まれて消えた。
「──チェ、タチェ」
男の呼ぶ声に我に返り、杯を持つ手が震えている事に気が付いた。
「悪かった。思い出させるつもりはなかった」
「……いや、良い。大丈夫だ。忘れるつもりも無い」
「俺に忘れろと言ったのは誰だよ」
「お前が覚えてても仕方ないだろう。嫁さんと子どもの事でも考えてろ」
持っていた茶を一気に飲み干し、代わりを店主へ告げる。程なくして新しい茶が入れられた杯が運ばれてきた。
メトセラへ戻った私たちを迎えたのは、歓待でも何でもない、ただの日常だった。形ばかりの報告書の提出を要求され、もう一度あの情景を思い出す拷問のような仕打ちも受けた。雪原に眠る隊員達は速やかに除名され、初めから何も無かったかのように処理をされていく。報告書を提出した後、あれだけ長期化した遠征にも関わらず説明が無いことは気にかかっていた。野盗の状況、今後の対応、一切が話にすら上がらなかったのだ。
隊は解散を言い渡され、男は失った片足を理由にそのまま騎士団を後にした。私を含め生き残った数名もそれぞれが別の隊へと割り振られた。まるで私たちが集まる事を恐れるように。それからの数年の間、一人二人と退団の知らせを伝え聞き、私は最後の一人となった。その頃にはもう、野盗討伐へ向かい冬の領土に立った隊の話は噂話の類にまで落ちていた。
「……やはりあれは、試験遠征だったと思うか」
男を見ずに私は尋ねる。男はただ無言で酒を飲み、小さく息をついた。
「だとして、どうする」
「……それは、」
後ろから笑い声が響き、私たちは会話を止める。先ほどテーブル席についた若者たちの笑い声だ。
あの隊員達とも、ああやって酒を飲み交わし、笑いあったのだ。あれは、メトセラを発つ前日だった。
振り返った私と男の視線に気付いたのか、若者のひとりが気まずそうな表情で、わずかに頭を下げた。
「……ほら見ろ。お前の顔が怖いから」
「お前、私の温厚な顔立ちを馬鹿にしたな」
若者に小さく手を振り、私たちはどちらからともなく笑う。気付けば酒場にも随分と人が増えてきていた。
「まだしばらくは、この町に居るのか?」
「どうだろうな。団からの要請次第だ」
「戻るつもりなんだな」
「ああ。まだやり残した事もあるしな」
怪訝そうな視線に気付き、男の目の前を手で払う。
「違う。そう物騒な事を考えちゃいない。教え子達が気になるだけだ」
「教え子? 指導係でもやってるのか」
「そうだ。お前が辞めた翌年に志願した」
「そりゃどういう風の吹き回しなんだ。合同訓練だって嫌がってたじゃないか」
男が笑う。
「受ける側と指導側は違うからな。しかし、私の訓練も嫌がられているんだろうな、地味でつまらんのだとさ」
「竜国の体術は受けが良いだろう」
「物珍しさで来る者も居たが、まあ、基本的に延々走らせるだけだからな。楽しい訳が無いな」
「……それは、俺への当て付けか?」
「ははは、お前の訓練もひどい手抜きだったからな」
「派手にやりゃ良いってもんじゃないんだ、ああいうのは」
「分かっているよ。……感謝している」
男が酒を置こうと体勢を変えた際、脇に立てかけていた杖が倒れた。倒れた杖を拾い上げる私の手を、男は見ている。
「……さっきの話だがな」
「何だ、訓練メニューならまだ覚えてるぞ」
「違う。大体お前の訓練メニューなら私が覚えている。ではなくて、」
もし、あれが本当に試験遠征であったとしたら。
私たちがいたずらに北上を命じられ、死にゆく様を望まれていたのだとしたら。
「……事実を突き止め、それを明るみに出すことも考えなかった訳じゃない。
雪に焼かれた手と背が痛む度に、私は何度でもあの怒りを思い出す。
ただ苦しかった。正当な理由があれば、この怒りから解放されるのだと思っていた」
男は黙って私から杖を受け取った。かつては剣を握っていた、その手で。
「しかし正当な理由など何処にある? 無いから、私たちはいとも簡単に捨てられた。
そういう所に、私たちは居たんだ」
それならば。
それはもしかしたら苦し紛れであり、ただの自己満足なのだろう。
メトセラを訪れるまだ成人をして間もない青年たち。目の前の相手に対峙をして、叩き伏せる術を乞われる事の方が余程多い。しかし彼らを生かすのは、結局のところ彼ら自身の体力と精神力でしかない。いかに剣技を磨き、百中の腕を持ったとして、雪原の前にはただ無力でしか無かったのだ。敵など居なかった。或いは、敵しか居なかったのかも知れない。
「……いざ出来ると可愛いもんだろう」
「何がだ」
「教え子だよ。わがままで、不遜で、自己主張ばかりをして」
「ははは、確かにな。どうせ今頃、私の不在を肴にサボっているんだろうよ」
手に持つ杯をいじりながら、私は少しだけ笑う。
「本当に小憎たらしいもんだ。ああ言えばこう言う。言う事など聞きやしない。
……そうそう簡単に、殺させて堪るものか」
人の増えた酒場を後にし、宿まで送ろうと歩みだした足を男の杖が止めた。
「送りは良い。これでも随分慣れてきたからな」
形ばかりと言えるような義足は確かによく使い込まれているように見えた。所々にある傷は、男なりに足掻いた跡なのだろう。
「明後日にはここを出るよ」
「そうか。遠いのか?」
「馬で半日と言ったところか。また折を見て仕入れに来るさ」
「あまり無理をするなよ」
「やめてくれ、急に年をとったような気分になる」
男は苦笑いを浮かべると、少しばかり不器用な歩き方でそのまま去っていく。男の後ろ姿が雑踏に消えるまで見届け、私も自分の宿へ足を向けた。