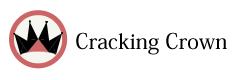燦々と輝く朝日に手で影を作りながら宿までの道を歩く。
今日は依頼はやめだやめ。とりあえず寝てから考えよ。
これから朝市でも行われるであろう市場は、商人達の天幕が立ち並ぶ。
見慣れたはずの麻布が光を反射して余計に目に染みる。
久々にでかい依頼を終えて、それなりの報酬を貰って、調子こいて飲んだのがいけなかったな。
抜け切らない酒の匂いがする。
ゴーダが飲みを早々に打ち切るのはいつものことっちゃいつものことで、
大体俺はその後も適当なメンツで飲み騒ぐか、どっかシケ込むかになるのもいつものことだ。
そのいつものことに変化があったとすりゃ、酔ったゴーダの惚気話がうざいくらいだな。
しーあわせそうな面でへらへら笑いやがって。
ああやだやだ、これだから春ってやつは。
いつもの道を曲がりかけて、足を止める。
今日はこっちじゃなかった。えーと、図書館を左手に曲がって、突き当りの三叉路は真ん中っと。
見えてきたのはいかにもゴツい出で立ちの古びた宿だ。
元は騎士連中の訓練施設だったんだそうだ。
軋む扉を開けると宿主の親父が俺を見て、一瞬戸惑ったような顔をした。
「あー、トスカだよトスカ。昨日あいさつしたろ」
手をひらひら上げると、そのまま親父は奥に引っ込んじまった。愛想が無ぇな。
部屋は確か2階の奥。
ポケットに突っ込んでた錆びかけた鍵で扉を開けて、ベッドにそのまま寝転んだ。
─ トスカ、いつまで此処にいる予定だ?
─ 別に決めちゃいないけど、何かあんの
─ 2週間ほど留守にする。その間、私の部屋を使わないか。
休暇申請を出してしまった手前、宿は一時的に退去しないといけないらしい。
しかし2週間なんて中途半端な期間のために退去準備を整えるのは骨が折れる。
かといって支払い続けるには少しばかり財布に重たい。
そんでまあ、一番手頃な俺に声を掛けたんだろう。
別に断る理由もない。
宿代を折半する条件で、俺はタチェの部屋の住人となった。
急いでいたのか気もそぞろだったのか、部屋には主が夕方には戻りそうな気配が残っている。
開きかけの本がベッド脇に転がっていたのでページを捲れば、杖術の指南書だった。
読みかけの指南書には途中に栞が挟まれ、ところどころページの端が折られている。
今度は杖に手を出すつもりなのか。まったく物好きだねえ。
本を適当なところに放り投げ、日差しの眩しさに腕を顔に押し付ける。
今日は暖かくなるんだろう。外からはガキの笑い声が聞こえ始めた。
* * *
北へ行くと言っていた。
行き先を告げるようになっただけ、進歩だ。
竜国を出る時も、騎士団に入る時も、あいつは一言も言いやしねえ。
見た目通り頑丈だからと、どこかで安心していたのもある。
実際、どんだけ師匠にぶん殴られても、吐いても、道場に通い続けていた。
何が楽しいんだと聞けば、そのものが楽しいと答える。
正気の沙汰じゃねえと、幼心に思ったもんだ。
だからこそ余計に、帰ってきたタチェの姿は、俺にとってもそれは衝撃的なもんだった。
騎士団員からの唐突な念話を受け取った時、俺はメンダヒルから南下している途中だった。
あの喧嘩か、あの依頼に足がついたか、思う巡らす間もなく、騎士は告げた。
─ せめて肉親の方が傍に。
メトセラ騎士団に所属している事は、手紙のやり取りで知っていた。
あいにく俺は念話は送れない。
何があったのか聞けないまま、俺はメトセラへ向かった。
騎士団なんざホントろくでもねえ。
まさか入り口で検問受けまくって二泊することになるとは思ってなかった。
タチェの名前を出したのが余計に拍車をかけていたのだと後から知った。
そういうこた初めに伝えておけよと念話相手の胸ぐらを捻り上げて、男に片足が無いことに気付いた。
タチェは騎士団には居なかった。
居たのは、街の外れに近い場所にある小さな宿だった。
鍵もかけていない木製の扉を開けて、真っ先に鼻を突いたのは、血の匂いだった。
せいぜい形だけしか分からないようなベッドの上にタチェは居た。
ベッドの脇にとぐろをまく赤黒い包帯。
倒れた椅子は足が折れている。
カーテンは半分ほど、引きちぎられていた。
ひと目見りゃ分かる。尋常じゃない。
「……タチェ」
俺の声にゆっくりと上げたその顔を、今も忘れられずにいる。
* * *
3日過ぎ、4日過ぎ、結果として2週間近く俺はその宿に滞在していた。
主に居てくれと懇願されたからだ。
宿代浮いてしめたもんだと思ったのは、1日目の夜だけだった。
真夜中、それも明け方に近い時間に決まってタチェは荒れた。
悪夢を見て起こされ、ここが何処なのか分からなくなるらしい。
明け方の冷えた空気を吸い込むだけで鮮烈に思い出すという悪夢を、ついにタチェは自分から話すことはなかった。
毎晩のように暴れるおかげで傷は何度も開き、その都度赤黒い包帯のとぐろが増える。
それでも最後の砦のような自制心が働くのか、俺に直接手を上げることは無かった。
あんな状態で何発か食らったところで、痛くも痒くもねえのにな。
タチェを抑えこみ、ベッドに座らせ、ここはメトセラだと言い含め、明るくなる頃にようやくもう一度寝入る。
その繰り返しだった。
あれは1週間を過ぎた頃だった。
いつも通り腕に包帯を巻き、背に薬を塗りこむ。
剥げた鱗は、いまだに生え変わる兆しはなかった。
あんだけ荒れてるのを繰り返してりゃそれも道理だろうが、恐らくこの傷はこのままだろうと経験則から思う。
もともと竜人は寒さに強く出来ちゃいない。
タチェをそのままベッドに押し込んで横にさせる。
外からは夕刻を告げる鐘の音が響いていた。
俺もタチェも睡眠は長くない。
どうせあと数時間もしないうちに目を覚まし、また暴れるのだろう。
俺はそれを抑えこみ、ここが何処なのかを教え、呟く名前の主は死んだのだと、また伝えるんだろう。
やりきれなかった。
俺も確かに消耗し始めていた。
その夜、タチェが暴れることはなかった。
脇のソファで眠っていた俺が気配に目を覚ますと、ベッドに半身を起こしたタチェが居た。
何をするでもなく、ただ手元を見つめ続ける姿に何処か寒気がしたのを覚えている。
タチェの手元にはネックレスがあった。
俺も揃いのものを持っている。
家をでる時にお袋が持たせた、古竜を象った飾りのついたネックレスだった。
「……祈りは、」
俺が起きているのか否かは、恐らくタチェにとって問題では無かったんだろう。
「届かない、何も」
ひとりごとのように呟くその声音には明らかな怒りが滲んでいた。
そして部屋に、微かな金属音が響く。
それがネックレスを引き千切った音と知ったのは翌朝だった。
* * *
10日を過ぎる頃には、ようやく夜中に暴れる癖も収まった。
とぐろ巻きの包帯にも血は混じらなくなった。
我ながらよく付き合ったもんだと本当に思う。
体力は戻らないが、後は大人しくさせておけばどうにかなるだろう。
竜国までの帰路を思い、船の手配と宿の引き払いを考えていた俺の予想は、あっさりと裏切られた。
「騎士団に残るだァ!?」
素っ頓狂な声を上げた俺を見て、タチェが頷く。
「おいおいおいおい、冗談だろ、勘弁してくれよ。何のために俺がずっと残ってたと思ってんだよ」
「それは……本当に迷惑を掛けたと思ってる、でも」
「迷惑とかそういうんじゃねえんだよ。大体お前、俺に今まで迷惑かけた事なかったとか思ってんの」
まだやる事があると言うタチェは強情だった。
下手に動けるようになってたもんだから抵抗もするわするわ。
こんな事になんなら、大人しいうちに無理にでもメトセラを離れりゃ良かった。
結局、頑として首を縦に振らないタチェに根負けしたのは俺の方だった。
タチェの団戻りと合わせて、小汚え宿も引き払う。
数カ月は、俺に連絡を寄越した騎士から念話が来ていたが、やがてそれも無くなった。
義足では指導役としても残るのは難しいと言い、やはりタチェを団から抜く事は出来なかったと謝られた。
* * *
外から聞こえた爆発音にビビって起きた。
何事かと窓を開けると、宿の路地裏でガキどもが爆竹鳴らしてやがった。
しかも野良犬に当てようとしてやがる。
悪ガキっつーのはどこにもいんだな。
眼下のガキどもにうるせえと怒鳴ると散り散りになって逃げ、残された野良犬は逃げもせずに俺を見上げていた。
「んだよ、食うぞ」
俺の言葉が通じたのか野良犬は歩きだそうとするが後ろ足がびっこを引いている。
何だよ、逃げらんねえのか。
タチェの部屋は二階だ。階下の騒ぎが筒抜けになる程度には天井も低い。
窓からそのまま飛び降りて、ビビる犬の首根っこを掴んだ。
きゃいんとか鳴くなよ。俺が虐めてるみてーじゃんか。
「……タチェなら少しは治してやれんだろうけどな」
ポケットに突っ込んでた布切れで後ろ足を包んで、抑えていた頭を放す。
おまけだ。持ってけ。
魔力盾をかけると犬はそのまま一目散に逃げ出した。
ひょこひょこと片足を引きずりながら去る後ろ姿に、あの騎士を思い出した。
2週間を終える前にタチェは戻り、俺は早々に宿を出ることにした。
約束なのだから終えるまで滞在して良いという申し出は断った。
あの飾りっ気も何もねぇ部屋は、余計なことばっか思い出して疲れるんだよなあ。
戻ったタチェの様子も別段晴れやかには見えず、それがただの旅疲れなのか違うものなのかまでは聞いていない。
もっと楽に生きりゃ良いのによ。
勝手に背負って、勝手に祈って、まったく何が面白くて生きてんだかな。
俺には分かんねえや。
* * *
片足を引きずった犬に妙に懐かれるとぼやきを聞きながら、タチェの金で飯を食う。
博打ってのは本当に罪深い。
これ明日からまじでどうしようと目の前の肉を頬張り、ちらちらと肉に当たる光に気が付く。
何かの反射のようで、時折消えながら揺れている。
反射の元を辿るうち、タチェの首元にそれがあることに気が付いた。
あの日、引き千切っていたネックレスがそこにはあった。
幾分短くなっちゃいるが、古竜の他にもう一つ小さな石がついている。
ヒビのような紋様の入ったその石が、酒場の照明を反射してちらちら揺れていた。
お互いもうガキじゃねえし、別にどうしたなんか聞くつもりもない。
だがまあ、時折懐かしむようにいじる姿を見る限り、悪いもんじゃあないんだろう。
まったく、厄介なのに手を出す猛者も居るもんだ。
贈り主に半ば同情を感じながら、目の前で笑うタチェに茶を渡した。