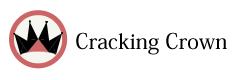中央の図書に用事があるとだけ言い残し、ふらりと消えていた。
ネイアンが留守にするのは大抵が突然のことで、戻るのも突然のことだ。
帰り際にこちらに寄るらしい。
届けられた早文にはおおまかな到着予想時間と、ネイアンが好む茶の名前が記されていた。
「チハヤ」
木組みの露台で花を干しているチハヤに声をかける。
前掛けをつけたチハヤの姿は、街にいる給仕のようでもある。
「水を持って来る。先にネイアンが来るかも知れない、通しておいてくれ」
チハヤが頷くのを確認し、小さな手提げの桶を持って家を後にした。
足に巻いていた布をほどき、柔らかく岩をおおう苔を踏み歩く。
つけた足跡にはじわりと水が浮き、すぐに苔に染み込み消える。
これだけ豊かに水を飲むなら、新しい種をじゅうぶんに育み、じき杜木が生まれるだろう。
足を止めて苔の感触を確かめていると、若い草塊が揺れ、つけたばかりの花を私に見せ付ける。
触れるとガクごと花を落とした。
まだ香りも薄い。今年はじめてつけた花だ。
お前にはまだ早いと撫でると、不服そうにさらに揺れた。
杜の色が変わっていないことに安堵しながら、枝の指す方へ進む。
そろそろ新しい水庭が出来る頃だ。
今出来ている水庭は4つ。あと2つは欲しいと考えていた。
あまり多くても木々も苔も余して腐らせてしまうが、客人向けの水庭は杜深く、頻繁に訪れるには向かない。
できれば家の近くに寄せたいのだが、それはニーバルが帰化してからの話だ。
時間ならある。あせることもない。
地を巡るつる草がやがて一方向に吸い寄せられていく。
木々の色がわずかに変わり、そこに新しい水庭があるのを確かめた。
水庭からは木の色を吸い上げた水が染み出し、ときおり水泡をあげている。
チハヤに飲ませたらまた高熱を出すはめになるだろうが、ネイアンなら大丈夫だろう。
以前から新しい水庭の味に興味を示していた。
まとめていた髪をほどき、水に浸す。
広がった髪は水に沈み、ゆっくりと重みを増していった。
戻ると、家の前には四足が一頭で大人しく草を食んでいた。
太い角には虫除けのランタンが提げられたままだ。
ちょうど四足の陰になっていた辺りからネイアンが顔を出し、片手を上げる。
私もこたえるように手を上げ、家へと招き入れた。
「ちょうど水庭が出来ていた」
つる棚から取り出した茶葉を小鍋にうつして火にかける。
ふつふつと沸き出した水は、木の色が抜け、やがて茶葉の色がひろがった。
木ベラで混ぜる私の後ろでは、ネイアンが両手に提げた荷物をほどいている。
「それはちょうど良かった。そろそろそんな時期だと思っていたんだ」
ネイアンが木箱だの布包みだのを置きながら笑う。
布をほどくと中から紐で綴じられた本が出てきた。
いくつかはそのまま布でくるみ、いくつかはテーブルに乗せる。
「ユンファから聞いたよ。まじない布があるんだって?」
「ああ、それなら」
小鍋を火からはずし、ネイアンの後ろを指差す。
キチネットからすぐ近くの物置だった部屋を、今はチハヤの寝室にしている。
件のまじない布は、擦り切れかけた仕切り布の上からあてがう事にした。
あの石無しはあまり意に介さず、好き勝手な場所で眠りこけているが。
「裁つには惜しかったので、仕切り布にしている」
「いっそ裁たれた方がマシな使い方だね」
ネイアンが軽口を叩きながら腰を上げ、ふらふらと仕切り布に近付く。
剥がして良いかと聞かれ、頷いた。
茶葉からすっかり色が抜けたのを確認して、小鍋を火からおろす。
煮詰まった茶を金属製のカップに分け、摘んでおいた蜜花をいくつか浮かべる。
軽くカップを揺すれば蜜花はそのまま溶けて消えた。
「何だ、思ったよりも新しい。まだ縫える樹種が居たんだ」
まじない布を手の平で撫でながらネイアンが椅子に腰かけた。
ネイアンの前にカップを置き、私は立ったままで茶をすすりながら布を見下ろす。
「縫えるものが減った訳ではないよ。私もニーバルから縫い方は教わっている」
「使う機会が無いの」
「それもあるし、そもそも売り物にならないから出回りにくいだけだろう」
心なしか残念そうなネイアンから布を受け取ると、露台からチハヤが顔をだした。
「ジュノー、花あとどうすれば良い」
「おや、久しぶり」
ネイアンが立ち上がり、チハヤの頭をわしわしと両手でこする。
こどもにする仕草だ。
「いつぞや熱を出した時以来だ。元気だったかい」
「元気、元気です。ちょっと、いたい」
ネイアンの両腕にがっしりと頭をつかまれたままのチハヤがどうにか抵抗をしている。
額に角をつきつけられ、私の方を見た。涙ぐんでいる。
「ネイアン、やめてやれ。角が怖いそうだ」
「失礼な。これまでのことを聞いてやろうと思ったのに」
手を離し、椅子に腰かけるとチハヤを手招き向かいの椅子をすすめる。
私とネイアンの顔を見比べながら、チハヤがおずおずと座った。
初めの頃こそ、もっとも谷部語に精通していたネイアンにあれこれ話しかけていたものの
その度に角の交流をされ、いささか怯えている様子だ。
外から吹き込む風が湿気を孕んでいる。
窓におろした布が風にあおられて揺れるが、差し込む陽は弱くなりつつあった。
「外の四足はあのままで良いのか」
「ああ、別に逃げやしないし、邪魔なようなら動かそうか」
「ではなくて、じき雨が降る」
「雨?それは困る。どこか雨よけになる木陰は無い」
「扉脇を使ったら良い。あの辺りは古いから四足に慣れてる」
飲みかけのカップを置き、ネイアンが外へ出る。
妙に静かなままだったチハヤが小さく息を吐いた。
慣れないうちは角の共鳴音だけでも耳につくと聞く。
うるさいかと問うと、首を振った。
単純にネイアンの交流が怖いだけのようだ。
「あ、雨降るなら、干してる花はあのままで大丈夫かな」
そわそわとしながら言う。席を離れたいらしい。
ここまで怯えられると、少しばかりネイアンが可哀相ではある。
「今日干したばかりだろう。水気は抜けていないだろうから今入れても変わらない」
「……そう」
「降りだしてきた」
ネイアンが戻るのと同じくして、雨粒の落ちる音がしだした。
細かい雨らしく、すぐにさらさらとした音に変わった。
カップから淡い湯気がたちのぼる。
湯気は私の肩もとあたりで消え、あとには茶葉の香気が残る。
この少しくせの強い茶をネイアンは好んで買い付けては、なぜか私の家に置いていく。
いわく私の杜の水と相性が良いらしい。互いにアクが強く相殺するそうだ。
本人は褒め言葉と言い張るが、さすがに私だってそれくらいは察することができる。
チハヤに匂いをかがせたら無言で目を逸らした。
裏の水場で空になったカップと小鍋を洗っているとチハヤの小さな悲鳴が聞こえた。
何事か、と思うのも慣れた。
どうせまたネイアンが隙を見て交流をしたんだろう。
戻れば案の定、椅子から落ちたらしきチハヤが転がっていた。
「……大げさだと思わない」
悪びれない様子でネイアンが肩をすくめる。
部屋にはまだ角の共鳴音がかすかに残っていた。
顔を洗ってくると言い残し、ふらふらとチハヤが水場へ向かう。
途中、敷き布につまずいた。
さらに水場の方から草むらに倒れこむ音がした。
「あまり苛めてくれるな」
「いいかげんに慣れてくれたかと思ったんだけどな」
ネイアンが私を手招き、額に角をあてた。
共鳴音が耳元で鳴る。
「彼の見た街の様子だよ。君も見てごらん」
ネイアンの手が私のまぶたに触れ、私は目をとじた。
とじた暗がりの先に細い線がつらなり、刺繍糸のように紋様を描く。
やがて紋様はおぼろげな街の様子を映し出した。
濃淡のある茶が染み出したような街はしだいに輪郭を持ち、ときおりひどく揺れる。
「チハヤは落ち着きがないね。キョロキョロしながら歩き回っている」
ネイアンが笑い声を含ませながら言う。
香辛料の並ぶ店先で店主が笑いながらいくつかの筒と壷を渡す。
チハヤの手がそれを受け取り、荷車に乗せた。
そして再び視界が街路に向けて揺れた時、見慣れた影を見つけた。
思わず声をあげた私にネイアンが角を離す。
「何か見えた?」
「ニーバルがいた」
「ニーバル?本当に?」
ネイアンは今度は私には角をあてずに目をつむる。
やがて小さな笑い声をあげた。
「本当だ。何をしてるんだ」
「酒でも探してるんじゃないか。私の酒は飽きたと言っていたから」
「何て俗っぽい樹種なんだ」
空には薄暗い雲の間から陽がさしはじめていた。
雨がやんだことを確認し、ネイアンが木陰につないでいた四足の引き縄をほどいた。
穏やかな顔立ちの四足は一度大きく身震いをして、葉が吸い切れなかった水滴を落とす。
また来る、と手を振るネイアンを見送るチハヤの顔には もう来るな と書いてあった。