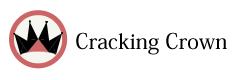「ここ、間違えてらっしゃいますよ」
「日付で良いのよね?」
「ええ、日付には暦ではなく、お生まれになってからの日にちを記入ください」
「ああ……そう、そうだったわね。ええと……」
「72と42日でございますよ」
「そうそう、そうね。いやね、だんだん無頓着になってしまって」
わたしの目の前でペン先を眺めていた青年が日付の箇所に指をそえます。
日付の箇所を指でなぞれば数字は跡形もなく消え、わたしはあらためて72、1、12と記しなおします。数字は紙の上で淡くひかり、すぐに濃紺になじみました。何度見ても不思議なものと思うけれど、目の前の青年は静かに「そういうものなのです」と頷くばかりでした。
宛名、季節のあいさつではじまり、日付とサインで締めくくられるまるで手紙のようなこれを書くのは、庭にある緑の薔薇が花をつけた時というのが青年とわたしのしきたりでした。わたしが生まれる前から続き、そしてわたしが居なくなった後にも続くしきたり。いつからあるのかと問えば遠い昔からと、いつまであるのかと問えば遠く先までと青年は答えます。その遠さがどれほどのものなのか、私には到底思い及ぶことではありませんでした。
サインを終え紙を渡すと、伏せられた青年の黒褐色の瞳が文面を追うように流れます。はじめてこれを書いたのは、確か十の冬。まだ呼び慣れなかった青年の名を宛名に、季節のあいさつは言われるままに書き記しました。内容には何を書いても良いと言われたものですから、まだ幼かったわたしは授業で習ったばかりの詩を得意げに記したのです。すぐに詩のつづり違いを指摘され、ひどく恥ずかしかったことをよく覚えています。
十の冬。十五の春。二十三の夏。二十六の秋。
紙をおさえる左手に指輪が増えた時、濃茶だったわたしの髪に白いものがまじり始めた時、ただただ連なり過ぎていく時間の中で、まるで季節など知らないように緑の薔薇は花をつけます。そのたび、時には願いを時には懺悔を書きしたためてきました。願いは叶うこともなく懺悔が解けることもなかったけれど、いつでも青年はそれを受け取り静かに懐にしまったのです。
「……この、お名前は?」
いつもなら何も言わずに紙をしまう青年がわたしに紙を見せ、記した内容を指でなぞりました。
「孫の名前よ。書いてはいけなかった?」
「いいえ、お嬢様たちのお名前なら私もよく存じておりますが……」
めずらしく困惑したような表情をうかべる青年は、まるで年相応のようにも見えました。
青年が指でさし示した箇所に、わたしは指輪を置きます。目の端には花弁を散らしはじめる緑の薔薇がありました。
「ミシェルはすこし神経質だけど気のつくとても良い子よ。シャノンはとにかく元気ね、それとあなたのことが好きみたい。エイミーは賢いから、もしかしたら家を出る方が彼女らしく生きていけるのではないかしら。それから」
「ヘレナ様、」
わたしの言葉をさえぎることも、青年にはめずらしいことでした。わずかに下がった眉。彼が困った時にするこの表情が、わたしは好きでした。それももう遠い娘時代のこと。
「多分ね、分かるのよ。わたしが書くのはきっともうおしまいなのよね」
かつてわたしのお祖母様と向かい合っていた青年の姿がまぶたに浮かびます。いつもせわしなく屋敷中のものごとを片付けていた彼が、ただじっとお祖母様の手元を眺めている姿はどこか神聖なもののように見えたものでした。あの日、お祖母様は祈りのように青年の額にキスをしました。そして訪れた冬の日、私は青年と向かい合いはじめてこの紙に触れたのです。
お祖母様が何を書いていたのか青年が明かすこともなく、わたしが聞くこともありませんでした。ただ、幾度となく書きしたためながら、お祖母様が何を書いてきたのか慮ることができるくらいには、わたしも歳をとったのでしょう。願いを記し、懺悔を記し、迷いをつらね、喜びを伝え、その先にはいつも彼がいました。変わり続けるわたしの前に、ただ変わらないものとして。
「ありがとう、長いこと聞いてくれて」
置いたままの紙を三つに折り、わたしは青年に渡します。しばしの迷いのあとで、青年は受け取り懐へしまいました。丸テーブルの上には指輪と羽根ペンだけが残され、緑の薔薇はすっかり散り終えていました。花弁すら残さないこの薔薇の花開いた様を、そういえばしっかりと見たことはなかったかしらと今さらながら少しばかりの寂しさを覚えます。
冷えた風が庭に吹く頃、聞き慣れた声がわたしを呼びました。
「おばあさま、もう冷えてきたわ」
「ええ、もう戻るわね」
「お前もこんな時間まで何をさせているの、身体に毒だわ」
「エイミー、良いのよ。わたしが散歩をしたかったの」
ため息をつきながらひざ掛けをわたしに差し出すエイミーの視線が、ふとわたしから逸れました。何かを探すような大きな目が庭のすみからすみへくるくると動きます。
「こんな薔薇、庭にあったかしら」
怪訝そうにつぶやくエイミーが何を見たのか、わたしと青年はおもわず目を見合わせました。エイミーの視線の先にあるのは緑の薔薇。それも、小さなつぼみをつけた。
「こんなに愛らしいつぼみをつけていたのね」
「おばあさまは知ってらしたの」
「ええ、もうずいぶん前からね」
きょとんとした顔のままのエイミーの頭をなで、わたしは立ち上がります。
テーブルに置いたままの指輪を彼女が知るのは、きっともう少しあとのこと。青年はいつもと変わらない様子で彼女を椅子に座らせ、あのしっとりとした紙を差し出し、宛名とあいさつを書かせるのでしょう。
彼女がしたためるものが喜びであれば良いと願うと同時に、彼が受け取るものも喜びであれば良い。
わたしは青年とエイミーの額にキスをしました。
お題:節目