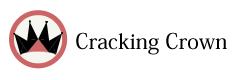夢を見ていた。
わずかにあけられた障子の向こうから聞こえる蝉しぐれ。握っていた金魚柄の団扇の先で、風鈴の影が揺れる。まだ滑りやすい青々とした畳の座敷を走れば、欄間のふくろうが私を睨めつけた。土間には竈に向かう母の後ろ姿。私を振り返ったその顔は強い日差しの影にある。母の口が何かを伝えるが私にはそれが聞こえない。私は言葉半分に頷きながら、ただただ遊びに出かけたかった。友人がいたのだ。彼と約束をしていた。
朝顔の鉢植えが並ぶ裏道を抜け、縦にひびの入った木製の電信柱を数える。曲がり角を抜けた三本目の脇にある苧麻(からむし)の茂みには、ちょうど子どもひとりが入リ込めるような隙間があった。幼い私は身体を滑り込ませ、ひんやりとした土を確かめながらなお走る。露草、姫女苑、蛇苺。目の端に過ぎる草花の名を私はまだ覚えていたらしい。どれも彼が教えてくれたものだった。向日葵は好かないと言っていた。種の重さに俯く姿が罪人のようで哀れだからと。
「水崎さん、点滴交換しますね」
逆光の中で、女性が私の腕に触れているのが分かる。脈を取るために手首に添えられた指はすぐに離れ、ペンの滑る音がかすかに聞こえる。明るいことだけは分かるものの、まぶたを開けるのも億劫だった。しばらく私の様子を伺うような気配の後で周囲がわずかに陰る。女性の声はすぐに隣のベッドへ向けられた。
汗ばむこともない空調と硬さの残る枕の感触の中で、私の意識は再びあの夏の日にまどろむ。
土の匂い立つ雨上がりだ。
足元に一瞬鋭い影が浮かび、遅れて鈍い雷鳴が響いた。縁側の先にある水たまりには、雲の切れ間から差し込む陽光が映る。折りかけたままの鶴を膝に、私は流れていく雲を見ていた。座敷の奥から彼の声がした気がして振り返れば、駆ける足先だけが見えた。足音が止まり、襖から手招く細い手首が覗く。
縁側、座敷、囲炉裏端。
彼の細くて白い手首がからかうように揺れる。指先は時に少年のようで、時に女性のようにしなやかに見えた。暗く沈み始めた家の中、彼との追いかけっこのおしまいはいつでも納戸だった。そして母に見つかって叱られるのは私だけだった。それでも勝手に友人を家に上げたことを報せる方がいけないことのように思われて、私はいつも黙って母の小言に頷いていたのだった。その母の後ろから小さな笑い声が聞こえていたとしても。
目を開ければすっかり消灯時間も過ぎてしまったようだ。どうやら息子たちが見舞いに来ていたらしい。小さな備え付けのテーブルの上には、古いノート束が置かれていた。あの家の処分も着々と進んでいるようだが、納戸に仕舞い込まれていた持ち主すら分からない物の処遇にだけ困ると漏らしていた。私の元へ持ってきたということは、おそらく私の名前でも書いてあったのだろう。
すっかり重たくなった腕でノートの縁をなぞれば、ざらりとした懐かしい感触がした。先刻まで見ていた夢も相まって、あの埃の匂いのする納戸の様子がありありとまぶたに浮かぶようだった。
今になって思えば、子どもにありがちな一人遊びの延長だったのだろう。未だ空想と現実が同じところにあった頃の話だ。快活に遊び回る少しだけ大人びた少年は、私の好奇心や憧れを掻き立てるには充分だった。
彼との遊びには細かな約束事が多くあった。
手を振ったら応えること。履物は右足から履くこと。正午には外に出ないこと。拾い食いはしないこと。打ちたくなったら息を三回吐くこと。ひみつの場所へは必ず同じ道を通ってくること。もちろん、誰にも言わぬこと。
約束事は厳格に見えながら、時々とても個人的(としか思えないような)な理由で追加されては免除されたものだった。一つ一つの些細な約束事の意味まで分からなくとも、それを彼と共有しているのだということが私にはとても特別なことに思えた。
伸ばしていた腕がずり落ち、ノートの束がベッドになだれ込む。数冊は落ちてしまったようだが、今の私には拾い上げることも難しい。かろうじてベッドの上でとどまったノートを持てば、中からぱらぱらと畳まれた折り紙が溢れだした。不格好に首の太い鶴、手裏剣は藁半紙で出来ている。
指で形を確かめるうち、慣れない感触に手を止めた。紙ではないその形に、私は確かに覚えがあった。これは私の作った笹舟だ。流すはずだった舟を私は持ち帰り、このノートに挟み込んだのだ。それは彼との約束事のひとつだった。そして彼と交わした最後の約束でもあった。
この夏を境に、彼は私の前から姿を消した。
いつから出会っていたのかも覚えていないというのに、不思議と彼と最後に交わした会話だけが鮮明に思い出される。あの頃の私と然程歳も変わらない少年だった。ましてや私にしか知り得なかった筈の彼は、まるで似つかわしくない大人びた顔で、私に話しかける。
─ 七つになったから、もう行かなくちゃならないよ
そう、あれは七つの夏の日だった。
─ その舟は流さないで持っておいで
それが最後の約束だから、と彼が私の手に瑞々しい笹舟を渡す。渡された私の手は彼よりも余程大きく、見遣れば彼の頭も私のはるか下にある。
もう会えないのかと問えば、彼は俯いたまま頷いた。ならばこれは受け取りたくなかった。
すっかり老いた私の中に、七つの私がある。七つの私が泣きじゃくっているのが分かった。次の夏も、その次の夏も、彼は居るものと信じていたのだ。無くなるものがあることすら知らなかった。
─ おしまいじゃないよ、おしまいにするっていう別の約束なんだ
彼が七つの私に話しかける。幼い私には分からなかった言葉のひとつひとつも、今すっかり彼を追い越して老いた私には分かるような気がした。俯いていた彼が顔をあげる。その目は、私を見ていた。
─ 無いことが僕がいた証拠だ。空いたその場所に新しいものを詰めるんだよ
私を見つめる彼の顔は、学友のようであり、幼い頃の息子のようであり、孫のようにも見えた。私の顔を見て、彼は満足げに目を細めた。
まぶたを開ければそこは暗いままの病室だった。散らばった折り紙、指先には水分を失った笹舟がある。
確かに私は 、彼のあった場所に様々な何かを宛てがってきたのだろう。
約束を変えながら、それで無くすこともなく。