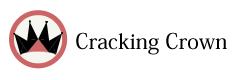その船では、髪の毛を切らないのが習わしなのだそうだ。
床に届きそうなほどに長い髪を束ねた大人たちと、ゆるく波打つ髪を跳ねさせながら走り回る子どもたち。邪魔ではないのかと聞くと、何故邪魔になるのかと聞き返された。彼らにとって髪は手足のように伸びて当然のものらしい。
「我々は古くから流れてきた民なので、先生には奇異に映るかもしれませんね 」
客人室で茶を淹れながら、案内役の青年が言う。彼の髪も例外なく長く、ゆるく編み込んで腰にまいてあった。茶からは香ばしい湯気がたつ。木目の鮮やかな客人室には丸いテーブルと備え付けのベッド。壁には蔓草で編まれたようなハンガーが並べられ、私のコートと帽子もそこに掛けられている。
テーブルに置かれたいくつかの書類を彼と見比べながら、私は依頼内容を確認した。
「ええと、期間は二週間ですよね。普段使ってる道具は持ってきてありますけど……」
「ああ、あらかじめお伺いしたものはご用意してあります。先生は道具だけお持ち頂ければ結構ですよ」
「あの、」
「はい?」
「その、先生ていうの、やめてもらっても……」
青年がきょとんとした顔で私を見るものだから、思わず手振りが大きくなる。そもそも私は医者でも学者でもない。
ただのしがない、
「髪結師ですし……」
* * *
私の願いは聞き届けられなかったらしく、青年は変わらず私を「先生」と呼び、船の住人たちもそれに倣って「先生」と呼ぶ。どこか腰のすわりの悪そうな私を見ながらも、「それが慣習なのです」と青年は姿勢を崩さなかったし、3日も経てばそれなりに慣れるものだ。
私にあてがわれた仕事は「先生」という呼び名とは程遠いようにも思えた。日替わりで訪れる人々の長い髪をすき、指定された精油をなじませ、時々ちがう結い方を教える。訪れるのはちょうど子どもから大人に差し掛かるような少年や少女たちだった。彼らの髪は、多少色の違いがあれども、みな癖も少なくしっとりと重たい。そして一房だけ、まるで差し色のように別色の束が混じっている。
「我々は”芽”と呼んでいます。大人にもありますが、子どもの方が色が濃いですからね」
日次報告のついでに尋ねれば、青年は特段隠すこともないように答えた。
「あなたにもある?」
「ありますよ、俺のは時期じゃないので目立たないですけど」
腰にまいたゆるい編み込みを解き、青年が私に見えるように一房取り出した。確かに、地の茶色とは違う濃い緑をした髪の束だ。その珍しさに触れようとする私の手を青年が止めた。
「あ、だめですよ。他の大人の”芽”にも触れてはだめです。普段も見えないように隠して編むんです」
言いながら青年は丁寧に、緑の房をしまうように編み込んだ。
「”芽”なら、いずれ咲くものなの?」
私の言葉に、青年は当然のように頷いた。そのために先生をお呼びしたのだと言う。
* * *
十日を過ぎ、私の元を訪れる少年や少女たちもそろそろ一巡しただろうか。元から良い質の髪ばかりだ。艶と水分に満ち、根本も太い。”芽”と呼ばれる色違いの一房は特に色艶が目立ち、まるで後から足したようだ。日を追うごとに色濃くなるようにすら見えた。使っている精油が違うのだろうか。それとも「船の民」の血筋なのだろうか。それなりに多くの人の髪を見てきたつもりだけれど、ここまで良い質を保ちながら伸ばされた髪を見たのははじめてだ。それもこんなにたくさん。
少しばかり巻いてやった髪に、嬉しそうに笑って部屋から出ていく少女と入れ違いに青年が部屋を訪れる。
青年の持っている盆を見て一瞬怯んだ。乗せられているのは、溢れんばかり、というよりもすでに盆から溢れている髪だ。私の髪色に合わせたのだろうことは分かるが、量が量だ。首でも乗せているのかと思った。
完全に怯んでいる私の目線と自分の持つ盆を見て、青年が笑った。
「すみません、明日から収穫祭なのでその準備をと思って」
青年が盆から髪の束をおろし、テーブルに乗せる。長い髪は折りたたまれ、収束する根本は頭の形を模した球形にある。要するにこれは……かつらなのだろうか。
「もしかして私がかぶるの?」
「そうですよ、我々では調整が出来ないのでご自分でして頂くことになりますが」
テーブルに乗せられたかつらに触れると、作り物の質感であることが分かった。何度も色を抜いては染められたのだろうそれは、毛先も乾いている。ほつれたように毛羽立つ毛先を見る限り、生き物の毛ではなく細い糸をより合わせて作られているようだ。
「……これは、毛先は切っても?」
「あー……出来れば避けていただけると」
作り物であっても切るのはやはりだめらしい。
櫛ですく前に毛先だけ先に糊で固めておく方が良さそうだ。汚れはほとんど無さそうだけど、一度ぬるま湯でほぐしてから精油で整えて……かつらをいじりながら思い巡らせる私の姿を、青年は愉快そうに眺めていた。
* * *
船の中がにわかに浮足立つ。収穫祭と呼ばれる祭りは3日、つまり私が期間を終えるまで行われるそうだ。
ひとつひとつの部屋に香の乗せられた小皿が置かれ、刺繍のされた布袋も渡される。これは祭りの最中に使うのだと青年が言っていた。船室の扉にもそれぞれ手のひらほどのタペストリーが掛けられているが、よくよく見てみれば織り方もモチーフも一貫性がない。あるものから飾りつけた、という意外とラフな彼らの気質が見えたようで少し親近感がわく。
廊下には飾り枠に入れられたランタンが吊るされ、普段は明かりが消されている階段までしっかり連なっていた。ランタンから漏れる光が飾り枠の影を写し取り、高くない天井や床板にまばらに飛び回る。採光窓は閉じられ、船の中を照らすのはランタンの光のみだ。まるで夕暮れの中にあるような橙の船内を、髪飾りをつけた子どもたちが駆け回る。
「祭りは広間で行うんです。いつもは閉めてるんですが、収穫祭の時だけ開放をして、」
私の道案内をかって出てくれた青年のあとを歩きながら、珍しい香と珍しい飾りの溢れる廊下を見回していた。私の頭には調整をしたかつらがあり、今の私の髪は腰まである。慣れない重さに頭を揺らす私を気にせず、青年は収穫祭の作法について説明を続けている。祭り、というものだからもっと仰々しい服装にでもなるのかと思えば、髪飾りをつけるのも子どもたちだけで大人は至って普段と変わらないように見えた。前を歩く青年もいつもと変わらず、あ、でも靴は新しいものかもしれない。
「聞いてます?」
「あ、すみません」
「まあ……えーと、3日目だけ広間に来て頂ければそれでも良いんですけど」
客室から迷路のような船内の廊下を進み、階段を降りるといっそう香の匂いが強くなる。広間へ続く廊下には天井から幾重にも布が垂らされていた。きめ細かく仕立てられた布にもランタンの灯りが透けて映る。
広間はすり鉢状のコンサートホールのようで、中心から八方へ線を引いたように均等に置かれたランタンが煌々と光る。目を引いたのは中央の吹き抜けだった。ゆるやかなアーチを描く柱は天井に向かいながらほどける。まるで根本から大樹の葉を見上げたような天井には夕暮れの空があった。
* * *
約束の3日目。私の仕事の期限の日でもある。青年の言うとおり、私はかつらを乗せたまま広間に居た。船中の住人たちが集まる収穫祭の最終日は、初日や2日目とは違ってそれはそれは静かに始まっていた。
房飾りをたっぷりとつけたフード付きのローブをまとった少年と少女たちが広間の中央、ちょうど吹き抜けの真下に集まっている。フードを取った彼らの髪は、高台から見た海のように豊かに波を打っていた。丹精込めてすいて精油を塗り込んだ甲斐があった。結い方を教えた少女が私の顔に気づき、かすかに微笑んだ。
古い言葉の歌だ。踵を打ち鳴らす音だけを伴奏として、人々が歌い上げる。円形の広間に響きながら降り注ぐ歌は、やがて天井に抜けていく。歌いながら人々が厳かにランタンの明かりをひとつずつ消していく。それでもなお、彼らの髪は美しくわずかな明かりですら返して光っていた。
……光っていた、ように見えた髪は、確かに光っていた。彼らの”芽”がひときわ鮮やかに、比喩でもなく、光を帯びているのだ。
筋だった光はゆるやかにうねり、丸まり、それはまるで蕾のようだ。ランタンの明かりがすべてなくなり、光る蕾が中央で花開いていく。吹き抜けの外を目指すように、確かな力強さをもって集まり伸びていく。幹がうまれ枝葉がうまれ、しなだれながら光が注ぐその輪郭は、帆布だ。大海原に風を受け、道に向かうための帆布だ。
人々の歓声が上がり我に返った。
ランタンには再び明かりが灯され、中央にいた少年と少女たちは嬉しそうに互いに抱きしめ合い、大人たちの拍手に応えていた。吹き抜けを見てもあるのはただ空ばかりだ。光も帆布も跡形もなかった。
「収穫祭は大成功です。先生のおかげです」
隣にいた青年が安心したように息をついた。未だに目の前で起こっていたことが理解しきれず、ぱくぱくと口を開けながら青年と中央を交互に指出すと、青年が笑った。
「我々は古くから流れてきた民なのです、先生。こうして、次の標を定めながら、ずっと」
* * *
船を降りたその翌日には、すでにもう船の姿は無かった。
私の手には、帰り際に渡されたいくらかの報酬と、刺繍の施された布袋がある。
中を覗けば胡桃のような大きな種がひとつ。街の外れにでも植えてみようか。きっとあの帆船のような、美しい芽を出すことだろう。