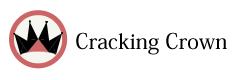月も星もない、ただただ群青の冴え冴えとした夜だ。
わずかな明かりが雪あかりに滲みながら点々と連なり、山裾へ消えていく。
あの山には熊が、あの湖には銀の鱗を持つ魚が眠り、木々はその枝先に氷をつけていた。
人々は四角く小さな居処で背を丸め肩を寄せ合い、小さな獣たちは新たな雪面に足跡だけを残し、やがてその足跡もすぐに埋もれていく。
私の吐いた息は粉雪となり、私の指先からは霜が降り注ぐ。
わずかな暖気をすら飲み込む私の凍気は、いまだ私の夜にある。
さあ早く眠っておしまい。
山の端を撫でれば空はいっそう深い群青に抜け、冷気だけが降り積もる。
夜はまだ深く長い。夜明けはまだはるか遠い。
道々には霜の柱を、晴れた空には凍える風を、水には氷を、山々には雪を。
そして温い血を持つものには静寂を、持たぬものには次の世代を。
瞬く星を追いやり、今しばらくはと指を立てる。夜はしんしんと更け、静寂が募る。
眠りのなかに彼らは新たな夢を得るだろう。
この夜はさなぎのようなものなのだ。
まばたきをひとつ、ふたつ。
夜はまだ深い。夜明けは遠い。あの丘を、あの海をこえてはるか。
どうか越えておくれ。もうしばらく夢を見ておくれ。
みっつ、よっつ。
しびれを切らした星々が瞬き始める。
海鳴りが連なる夜明けの気配を見出した。
いつつ、むっつ。
私の目が、それを捉えた。
さあ、連れてきておくれ。
腰を上げればそれはいっそう確かな明るさでもって私に届く。
深い夜はこれで終わる。 目覚めるための眠りが終わる。
そしていちばん長い夜を閉ざす番人の役目もここで終わる。
木々が氷を払い、大熊は寝返りをひとつ。雪ににじむ明かりは、じき空から降り注ぐ。
さあ、目覚める準備をしておいで。
日はまた昇り大地が芽吹く。
次に訪れるのは、霜を苗床に生まれ来る春だ、春だ、春だ。