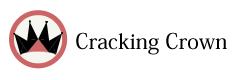発掘しておいた骨をこりこりとすり鉢で砕く横で、僕の可愛いゾンビがまだかまだかと口を開けて待っている。その口中は青黒い。本来あるべき歯も、どこかの誰かや、どこかの何かの歯なものだから奥歯が尖っていたり前歯が丸かったり不揃いだ。何を咀嚼する訳でもないのだから本来は不要なのだけど、歯を見せて不器量に笑う姿が大層愛らしいと思うので僕の好みで入れている。また新しい歯をどこかで掘ってこなくてはと思いながら練った土をやれば、器用に喉を動かして飲み込んだ。
「ずいぶんご執心だこと」
匙で土をやる僕を見ながら、呆れ声でスターシャが言う。
組んだ脚は長く、頬杖をついた指先は細く、青白い。スターシャはちょっとした力作だ。あの銀の髪を探すのにどれほどほうぼうを探し回ったか知れない。
「やっと笑ってくれるようになったんだよ」
「笑うねえ……」
土をやりながら僕が歯を見せると、この可愛いゾンビは真似るように歯を見せる。なんてことだ、本当に可愛い。
「やっぱり前歯は揃えてやりたいな。あと目も」
「揃えても、私たちは見えないのよ」
苦笑いするスターシャの目は片目が青で片目が茶だ。あいにくキレイに揃った目が見付からなかった。
土をねだるゾンビの指先が思案に揺れる僕の指先をなでる。すっかり力加減も覚えたらしい。手をなで返せば再び口をあけ、大人しく土を食んだ。
くぼんだ眼窩には木製の玉を入れてある。ガラス玉は彼らと相性が悪すぎて痛がるからだ。動かない木製の眼球であっても何かを覚えているのか、首を動かして僕の姿を捉えようとした。早く忘れておしまい。仕上げの骨粉を飲ませれば、満足げに肩を揺らした。
「見えない目に、ここはどう映っているのかな」
「どうもこうも真っ暗よ。光を見てた頃が思い出せないわ」
ただ、とスターシャが続ける。
あなただけがひどく暖かそうに見える、と。
「ふふ、まるで盲目の恋だ」
「そうね、私たちはあなたに恋してる。そう作ってあるんでしょう」
「嬉しいな。晴れて両思いという訳だ」
「そうやって誤魔化して」
スターシャが立ち上がり、僕の額にキスをした。触れる唇は冷たく、吐息すらない。その温度差に僕は安堵する。
僕は君たちに恋してるんだ。こんなに我侭でエゴイスティックなものが愛である訳がない。
だから、僕は君たちに恋をする。乞いて願う。ここに居てと。