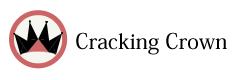「スターシャ、この子に名をつけたいのだけど、」
親鳥が雛にするように青黒いゾンビに土を食ませながらあなたが言う。蝋で固めてしまえば楽なのに、あなたは頑なにそうはしない。丁寧に丁寧に土と肉で身体を固め、動き回れるようになる頃には名をつけて屋敷の中に放す。時には真新しい服を着せ、時には真似事のようにテーブルにつかせる。私のように。
「そこらのモノから適当に持ってきてみたら?」
「何度か試してみたのだけどねぇ」
茶葉の入った瓶に貼られたラベルの文字を目でなぞりながら、あなたが言う。茶葉の名前を口中で呟き、意を決したようにゾンビに目を向けた。
「君の名は■■■■■■」
肝心の箇所はまるで雷鳴のように鈍くとどろく。まるで憎悪をすら感じられるような呪いの音だ。まだ名もないゾンビは怯えるように身を震わせた。
「ほらね、モノの名すら僕には許されてない。厳しいものだね」
すでに名付けられたものなら大丈夫なのだけど、とあなたは物悲しげにゾンビの頭を撫でる。私はあなたから瓶を受け取り、ラベルに書かれた綴りを指でなぞり確認しながら、ゾンビの額にそれをうつした。
「お前の名は、ディンね。おめでとう。歓迎するわ」
ディン、と名付けられたゾンビは舌のない口中でその名を復唱する。
その様子をあなたが嬉しそうに眺めていた。
* * *
スターシャ、という名は確かにあなたがつけたものだった。
目覚めた時、あなたは私をそう呼んで、泣きながら私の身体を抱きしめた。いまだ白く小さな虫の這い回る屍肉だけの私の身体を。けれど屍肉だけの私の身体は日に当たれば爛れ、風に吹かれれば崩れ、触れる水を腐らせた。いくら新たな屍肉を足しても腐敗の速度が上回る。あなたは夜毎日毎土を掘り返していた。
あなたは辛そうだった。
けれど、あなたにもまだ名前があった。
今となってはもう、口に出すことすら出来ない名前が。
そして泥水のような腐った血も流し尽くした頃、あなたは私に奇跡を見せつけた。あなたの捏ねる土は屍肉よりはるかに馴染み、私の身体にもう白い虫は湧かない。歯を埋めてもらい、舌をつくってもらい、そしてようやくあなたの名が無くなっていることに気付いた。あなたが持ち帰ってきたのは奇跡ではなく、呪いなのだと知るまでそう時間はかからなかった。
─ もう僕に名前は要らないんだ
まだ温かさの残る幼い屍体から眼球を取り出しながらあなたが言う。私にあてがい、満足げに笑った。
─ スターシャ、君を名付けたあとで良かった
「ディン。ディン、良い名だね。ディン」
あなたが愛おしげにゾンビの頭を撫で回し、新たに付けられた名を呼ぶ。
「ねえ、」
私の呼びかけにあなたが顔をあげる。
「私の名も呼んで」
少しだけきょとんとした表情を浮かべて、あなたは私の名前を呼ぶ。
名もないあなた、呼ばれることもなくなったあなた。
名を食われてなお、私たちを呼び続けるあなたのことを呼び返したい。
口中でつぶやこうとしたあなたの名は、呪いの響きで私の舌を痺れさせた。