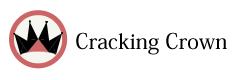「これと、こっちの黒いのと、あと前に買ったのはまだある?」
小さな瓶詰めが並ぶ店のカウンターであれこれと指をさすと、店主は慣れた様子で瓶詰めを棚から取り出して私の前に並べる。瓶詰めの中では色とりどりのインクがたぷたぷと波打っていた。
「えらくたくさん買い込むんだね」
「そうね、しばらく篭もらないといけないから」
青は試してみたけれどいまいち相性は良くないようだった。私のペンと一番相性が良いのは何の変哲もないただの黒。けれどそれだけでやり過ごせるほど仕事は 甘くない。編集の人から他の色を試してみてはどうかと遠回しに言われてしまった。要するに黒では物足りないということなのだ。
「この間受賞した先生はどれ使ってたの」
「おや、それを聞いてしまうのかい」
「参考よ、参考」
店主が笑いながら取り出したのは、鮮やかな黄のインクだった。これはずいぶん……かなり……癖が強そうだった。黄のインクが詰められた瓶を揺らすと、べったりと内側にあとを残した。
「……すごいの使ってたのね」
「まあ、こんなの使って書こうって方が珍しいね」
私はためいきを吐いて、店主に黄の瓶を戻した。さすがにこれを使う勇気はなかった。
黒に近い紫、相性は良くないけれど群青に、緑青。せめて何か新しい活路になってくれたらと、最後に明るい黄緑を選んだ。
「これくらいにしておくわ」
「茶は良いのかい」
「良い。茶は地味すぎて、受けが悪いの。分かってはいるんだけど」
「そりゃ惜しいね。アタシは好きだけどねぇ」
「ありがと、伝えておくわ」
袋詰にしてもらったインク瓶を抱えながら帰路につく。
帰ったらまずペンから今入っているインクを抜いて、洗って、新しいインクの配合を試してみなければならない。腕のメンテナンスは来週。それが終わったら部屋を整えて、配合したインクを飲ませて……。
見てくれだけは良いものに造ってもらったのに、私のペンはいまいち大衆に受けるようなものを書き出してはくれないのよね。ガラス玉の目で何を見ているのかしら。一度乾干しでもしてみようかしら。
ひとりぶつぶつとつぶやきながら、私は私のペンに目をやる。
まるで文豪然として佇むそれは、前につめたインク色の瞳で私に笑いかけた。